自己肯定感と自己受容の違いをわかりやすく整理|満たされない理由と本当の順番
「自己肯定感」と「自己受容」の違いを知りたい方も、たまたま覗いてくださった方も、こんにちは。
「自己肯定感」と「自己受容」って、どちらも“自分にOKを出す”ためのキーワードですが、実はその方向性が少し違うんですね。
私自身もかつて、「自己肯定感を上げよう」とあれこれ頑張っていたけれど、なぜかうまくいかない時期がありました。
それは、「自己肯定感」という言葉の中に、“そのままの自分を肯定する”とは少し別の意味が混ざっていたからなんです。
今回は、私の体験も交えながら、
このふたつの違いと、なぜ混ざってしまったのかを、やさしく整理していきます。
かなり読み応えのある記事になっているので、もくじを活用して、ご自身のペースで読んでください🌱
前提|“自己肯定感”という言葉には、いろんな意味が混ざっている
最近では、「自己肯定感」という言葉がとても広く使われますが、前提として知っておきたいことがあります。
それはこの言葉の由来です。
自己肯定感という言葉はどこから生まれた?
本来の心理学的な定義(アメリカの心理学)では、このように区別されていました。
① Self-acceptance:自己受容 = 自分を“評価せず”受け入れる状態
② Self-esteem:自己評価 = 自分を“素直に評価して”肯定できる状態
みなさんは、自己肯定感 = セルフエスティームと聞いたことはないですか?
実は…本来の訳は「自己肯定感」ではなかったんです。
「自己肯定感」という言葉は、
日本にあった純粋な和製心理語ではなく、Self-esteem(通常自己評価や自己価値と訳される)を和訳する過程で生まれた新しい日本語だったそうです。
つまり、意訳として生まれた言葉であり、この翻訳が、のちの自己肯定感ブームの出発点でもありました。
自己肯定感という言葉が混乱を生んだ理由
自己肯定感は、本来のSelf-esteemの定義よりも少し広がって、「そのままの自分を肯定する」という意味でも使われるようになりました。
そのため、現代では
「自己肯定感」 = 自己受容(Self-acceptance)+自己評価(Self-esteem)
つまり、「自分を評価しない、けれど評価する」という、相反するベクトルを内包した言葉になったんです。
そこが混乱ポイントでもあるんですよね💡
私も、まさにここで混乱していました。
ここからは、混乱しやすい自己受容・自己評価・自己肯定感の3つを改めて整理しながら、「自己肯定感を上げても満たされない理由」を紐解いていきましょう。
自己受容(Self-acceptance)とは?|ありのままの自分を認める生き方
自己受容(Self-acceptance)は、「できない自分」や「弱い自分」も含めて、ありのままを受け入れている心の状態のこと。
良い・悪いの判断や評価を手放し、「今の自分」をそのまま受け入れられる状態です。
何かができても、できなくても。
他人に評価されても、されなくても。
この土台があると、感情が揺れても、自分の中心に自然と戻ってこられる。
そんな安心感のベースになります。
例えば、失敗をしても、今落ち込んでいても、「そんな自分でいていい」と思える。
それが、自己受容が育っているサインです。
また、「自己否定」は、自己受容の反対にある状態です。
「ダメな自分を直そう」ではなく、「今の自分を受け入れる」と切り替えた瞬間から、自己否定のループはゆっくりほどけていきます。
🌱 自己受容(Self-acceptance)
ありのままの自分でOK。「自分がいつでも戻って来られる場所」のようなもの。どんな自分でもいいと思える土台があると、心は自然と安定し、安心感をベースに生きられるようになります。
自己評価(Self-esteem)とは?|“できる自分”を支える心理的機能
自己評価(Self-esteem)は、本来は「自分のことを価値ある存在として評価できている」状態を指します。
もともとは社会生活をうまく送るための心理的な機能です。
💡 英単語のesteemは、「~を高く評価する、~を尊敬する」という意味
つまり、Self-esteemとは、実際にできている自分を卑下せず、自分で自分を素直に“高く評価する感覚”を表す言葉なんですね。
自己評価が健全に機能しているときは、自信の土台になったり、やる気が自然と湧いたり、人間関係が安定しやすいです。
例えば、良い成果が出た時に素直に「うまくできたな」と喜べたり、誰かに褒められた時に「ありがとう」と受け取れる状態です。
外の評価に過剰に振り回されず、自分の努力や成長を自分で認められるんですね。
一方で、自己評価が低いと、実際にはできているのに「できていない」「自分なんてまだまだ」と感じ、自分を卑下して、追い込んでしまうことがあります。
結果として、焦りや不安が増え、他者の評価にも振り回されやすくなるんです。
🌱 自己評価(Self-esteem)
自分の努力や成長を自分で認められる状態。行動の燃料のようなもの。うまく使えば前に進む力になるけれど、足りないと動けず、そればかりを求めると条件にしばられ燃え尽きてしまいます。
自己肯定感とは?|日本語で使われる意味
先の章でも触れた通り、「自己肯定感」は、Self-esteemという概念が日本に入ってきた際に生まれた意訳で、その後、日本独自の意味合いで広がった言葉です。
自己を肯定する感覚か…
それが「そのままの自分を無条件に肯定する(=自己受容)」なのか、
「できている自分を卑下せずに素直に肯定する(=自己評価)」なのか、
どちらを指しているのかが、ちょっと曖昧ですよね。
そのため、人によって3つの解釈が混在しているように感じます。
① 自己受容として:ありのままの自分を肯定する
② 自己評価として:できている自分を肯定する
③ 自己受容+自己評価として:ありのままの自分も、できている自分もどちらも肯定する
※ 現在は一般的に③の解釈が多いようです。
みなさんは、「自己肯定感」をどのように解釈していましたか?
そもそも、そのままの自分を無条件に受け入れることと、うまくいっている自分を高く評価すること、このふたつって同時に成り立つのでしょうか?
私の実感としては、まず自己受容の土台が育ってから、自己評価を活かすことが大切。
自己受容の上に、自己評価がオプションのように乗っていることが健やかな自己肯定感なんじゃないかと思うわけです。
🌱 自己肯定感
一般的には、自己受容(Self-acceptance)と自己評価(Self-esteem)のハイブリッドな心の状態を指す。そのままの自分を肯定している上で、「自分には価値がある」という自己評価もあります。
自己受容・自己評価・自己肯定感の違いを整理する
ここまで、それぞれの意味や成り立ちを解説してきました。
改めて、この3つの違いを表で整理してみましょう。
自己受容・自己評価・自己肯定感の比較表
見る角度 |
自己受容 |
自己評価 |
自己肯定感 |
自己肯定感 |
|---|---|---|---|---|
本質 |
評価せず「そのままの自分でいい」と思える | 「できる」「認められる」自分を肯定できる | 自己受容と評価のバランス(揺れやすい) | 自己受容の土台の上に自然に育つ自分の価値(安定している) |
意識の方向 |
内に向かう(ありのままを受けとめる) | 外に向かう(成果や評価に反応する) | 内と外を行き来して調整しようとする | 内に根を下ろしながら外へ広がる |
心の状態 |
静けさ・安心感 | 自信・やる気 | 安心と自信の間で揺れる | 安心の上に健やかな自信が育つ |
条件
| ||||
反対の状態 |
自己否定(「こんな自分じゃダメ」) | 自己卑下(「どうせ私なんて」) | 自己否定または自己卑下(両面で揺れる) | 一時的に自己否定や卑下が出ても、すぐ戻れる状態 |
自己評価を上げようとしても満たされなかった理由|私が気づいた本当のこと
ここからは、私が「自己肯定感」への勘違いに向き合ってきた体験を、少し振り返ってみます。
当時、なんとなくの生きづらさを感じていた私は、
「自己肯定感が低いから生きづらいのかもしれない。上げたら、きっと生きやすくなるかも。」
と思っていました。
でも、その頃の私は、自己肯定感が「どうにかして自分を肯定すると、得られるもの」と誤解していたんですよね。
「そのままの自分の肯定」なのか、「何かをした自分の肯定」なのかも曖昧に理解していました。
私が試した「自己肯定感を上げる方法」は、実は自己評価を上げる方法だった
「自己肯定感を上げる方法」をみなさん試したことはありますか?
私がよく目にしたのは、このような方法でした。
🌼よく見る自己肯定感を上げる方法
① ポジティブ思考を身につける
否定的な考えを手放して、前向きに捉える
② 自分を褒める・承認する習慣を持つ
一日の終わりに「今日の自分を褒めるノート」などを書く
小さな成功体験を積み重ねて、自信を育てる
③ 自分を否定しない言葉を使う
「どうせ」「無理」などの否定語を意識して使わない
④ 比較をやめる
他人との比較ではなく、過去の自分との比較にフォーカスする
⑤ 人からの肯定的な評価を否定せず受け取る
褒められたり、「ありがとう」「助かったよ」と言われたときに、「いえいえ」ではなく「うれしい、ありがとう」と受け止める
※ どれも、「自分の評価を自分で上げる」「自分をよく思う」練習
どれも一理あります。
でも、効果が続かないんです。
確かに、その瞬間は前向きになれるけど、すぐに元に戻る。
「もっとポジティブにならなきゃ」と思って頑張るほど、
ネガティブに考える自分を責めてしまったり。
気づけばまた、自己否定のループに戻ってしまう。
今思えば、どれも「自己評価を高める」アプローチでした。
つまり、「何かした自分をきちんと肯定する」方の自己肯定。
自己卑下をしている場合には、効果的かもしれません。
でも、自己否定がある場合は、効果がなかなか継続しません。
多くの人がハマる“自己評価ループ”
このループは、多くの人が自己肯定感をまず上げようとして、陥るものではないでしょうか。
♻️多くの人がたどる自己否定ループ
自己否定で苦しい
↓
「こんな自分じゃダメだ」と感じて
↓
「自己肯定感を上げよう!」と努力する
(でも、実際には自己評価を上げようと努力している)
↓
「上げなきゃ」という時点で、「このままの自分ではダメ」とジャッジしている = まだ“自己否定の構造”の中にいる
↓
繰り返し
みなさんも、こんなループにハマったことありませんか?
そうなんです。
「自己否定 → 自己評価を上げよう」とする動きって、自己否定の延長線上で行われがちなんですよね。
私が本質的にしたかったのは自己否定をやめることだったと思います。
でも、「自己評価の意味を含む自己肯定感」を高めようとしていたため、そもそもの方法を間違えていたということです。
このループに気づいたとき、はじめて「あ、これは”そのままの自分を受け入れること”が足りてなかったんだ」と腑に落ちたんです。
それは、自己受容。
自己肯定感の前に育てたい“自己受容”という土台
この気づきから、私ははっきりとわかりました。
「自己受容を育てること」と「自己評価を高めること」は、まったく別のアプローチだということを。
「自己受容」の土台がない状態だと、「自己評価をいくら高めても一時的で不安定」になりがち。
また、先の章で分類したように、自己否定の対極にあるのは「自己評価」ではなく「自己受容」。
自己否定で苦しいときこそ、自己評価や自己肯定感を育てる前に、まず「自己受容」を土台にすることが鍵なんです。
🌱 自己評価も大切
けれど、自分の中心に据えてしまうと、条件付きの自信になってしまう
「自己受容」という土台があってはじめて、自己評価は健全に機能する
自己受容を意識したら、心が軽くなった理由
自己否定と自己肯定感(と思っていたけど実は自己評価)の間を行き来していた私が、そのループから抜け出せたのは「自己受容」という鍵を見つけたからでした。
正直その頃は「自己受容」という言葉すら知らなかったので、「そのままの自分を許す」「そのままの自分を受け入れる」と表現していたと思います。
では、当時の私が実際に意識していたことを挙げてみます。
💡自己受容のヒント
① “変わらなきゃ”ではなく、いまここにある自分をそのまま抱きしめる
② 湧いてくるネガティブ感情を否定せず、「今の気持ちをそのまま感じる」ようにする
③ できない自分でも、どんなネガティブな自分でも、「そう感じるよね」「そう思うよね」とその気持ちに共感してあげる
④ 他人の評価が自分全てを決めるわけではないと理解し、自分がまず自分を認めてあげる
すると、不思議と心の緊張は解けていき、しばらくすると「今のこの自分でいいんだ」と感じられるようになっていました。
そうして少しずつ、“頑張らなくても安定していられる自分”に変わっていったんです。
📚 より詳しい自己受容を育てる自己対話の方法の話はこちら
🌱こころが軽くなる順番
① 自己評価を上げるより、自己受容を育てるほうが先
② 自己受容ができてくると、肯定しようと努力しなくても、自然と自分を肯定できる感覚が育っていく
③ 自己評価は、それから高めても、高めなくてもいい
※ これはあくまで私の実感によるおすすめです
まとめ|自己受容ができると、自己肯定感も自然に育つ
土台に自己受容があると、どんな時も揺れにくくなります。
そして、自分のいちばんの味方が自分だという安心感は、すべての素地となります。
自己受容が深まると、その上にできる感覚(自己評価・自己効力感)や、自分を信じる力(自己信頼)が自然と枝葉のように育っていきます。
自己受容は「どんな自分も大切にできる土台」、
自己評価は「できる自分」を支える力。
そして、その二つが調和していくと、しなやかで健やかな自己肯定感になっていくのです。
まずは、できる・できないよりも、「今ここにいる自分」をそのまま認めてみませんか?
「ありのままの自分を認める」ことは、自分をやさしく支える大きな力になります🌱
ここまでお読みいただきありがとうございました。
この記事が、少しでも皆さんの生きるヒントになりますように。
それでは、また次回の記事でお会いしましょう〜🍵
📚 自己受容をもっと深めたい方へ、こちらの記事もどうぞ
📚 自己受容を育てる自己対話(内観・内省)の方法はこちらから
〈 今回の記事のまとめ 〉
- 本来のSelf-esteem(自己評価)は「自分を価値ある存在として評価できる感覚」
- Self-acceptance(自己受容)は「評価せずに、どんな自分もまるごと受け入れる安心の土台」
- 日本語の「自己肯定感」は、この2つが混ざった“受容+評価”のハイブリッドな概念
- 多くの「自己肯定感を上げる方法」は、実は「自己評価を高める」アプローチになっている
- 自己評価を上げる前に、まず「自己受容」という無条件の土台を育てることが大切
- 自己受容が深まると、肯定しようと頑張らなくても、自然と自分を肯定できる感覚が育っていく🌱
🌱 自身の「性質・傾向」を知って、
見えなくなってしまった「本音」を一緒に探す、自己対話ナビゲーション型セッション
📚 あわせて読みたい記事
🔍 読みたい記事がありませんか?このページでは、関心ごとから記事を選べます。


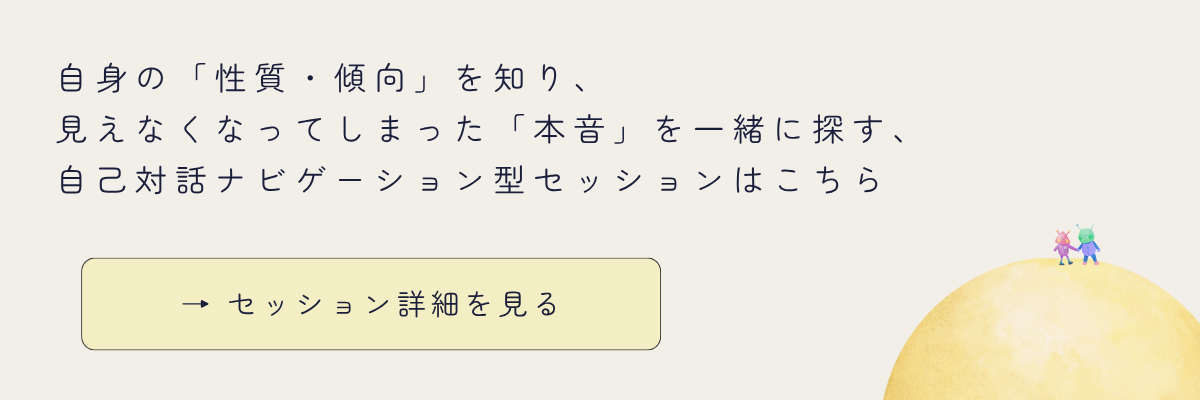



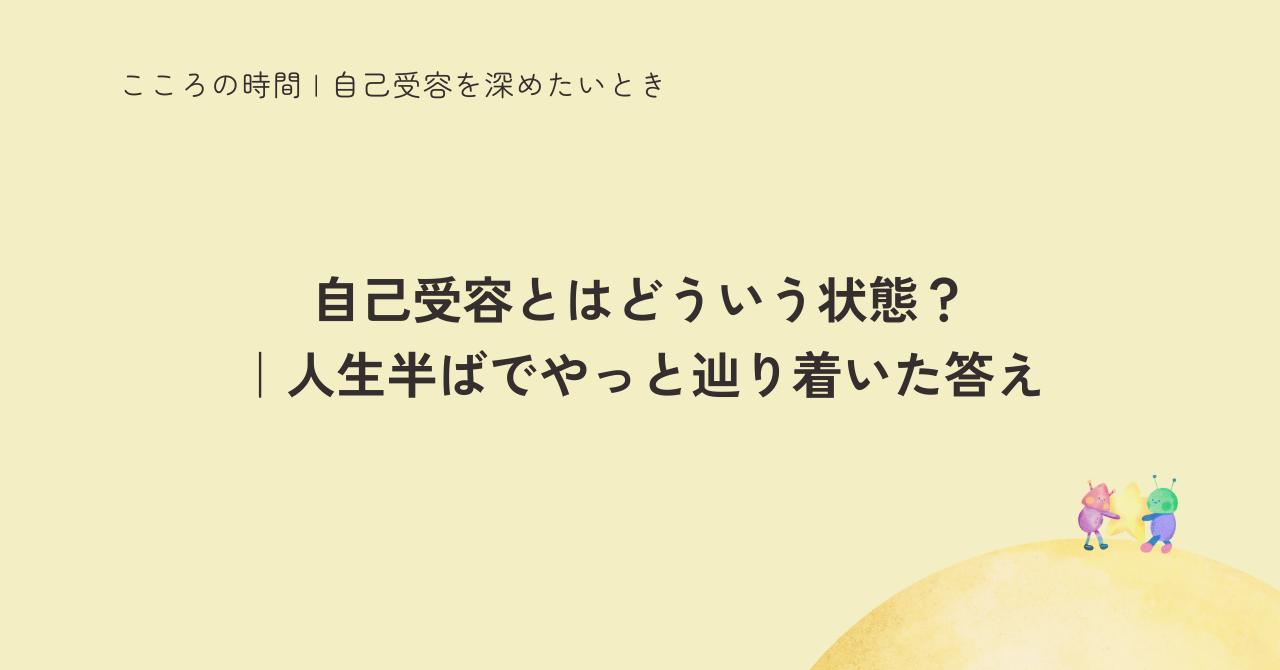
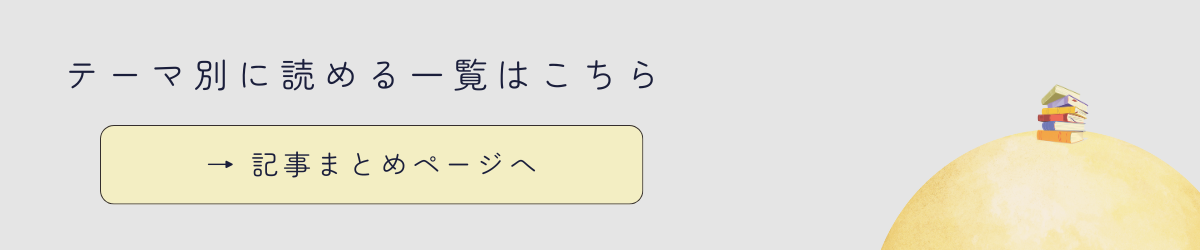
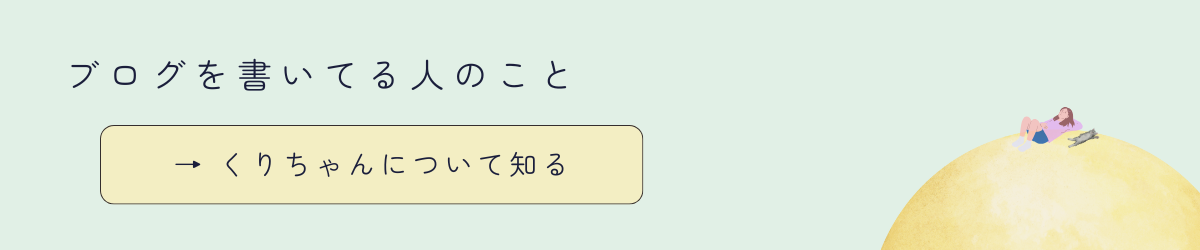
「くりちゃんとお茶しよ」は、私が心から好きで始めたもの。なのにいつの間にか“そうあらねば”に縛られていた。そんな自分にふと気づいた日の気づきです。不定期ショート記事。