DoingとBeing、どちらが先?|自己対話で見直す在り方と行動
とにかく動くのが好きな方も、まずは心を整えてから進みたい方も、こんにちは。
みなさんは、「Doing」と「Being」という言葉、耳にしたことはありませんか?
心理学やコーチング、マインドフルネスなど、さまざまな場面で語られる言葉ですが、実際にどう大事で、どう向き合えばいいのかは意外と分かりにくいものです。私自身、このテーマに長くモヤモヤしてきた経験があります。
今回は、そんなDoingとBeingを自己対話と絡めて整理し、少し生きやすくなるヒントをお届けしようと思います。
DoingとBeingの意味と違いを整理してみる
まず初めに、DoingとBeingの定義を整理しておきましょう。
それぞれ、こう表せます。
・Doing = 外側への作用(社会や他人にどう働きかけるか)
・Being = 内側の状態(自分がどんな心でいるか)
哲学や心理学、コーチングなど、分野によって少しずつ表現は違いますが、まとめるとこんなイメージになります。
・Doing = 何をするか(成果・行動・役割)
・Being = どんな在り方でいるか(存在・心の状態・価値観)
現代の自己啓発や生き方系では、次のようにも表現されます。
・Doing = スキルアップ、社会的な役割や結果
・Being = 心地よさ、自分らしさ
DoingとBeingの違い、少しイメージができたでしょうか?
この記事では、わかりやすいように「Doing=行動・社会的成果」「Being=在り方・自分らしさ」として扱っていきます。
Doingに偏りやすい現代社会
これまでの社会では、どうしてもDoing(行動・社会的成果)に偏りがちでした。
「行動こそ正義」「成果を出すことが価値」という空気の中では、Being(在り方・自分らしさ)を見失うのも当たり前ですよね。
心理学の分野では、カール・ロジャーズが「人はDoingよりBeingに価値がある」と語っています。マズローもまた、成果や役割ではなく「その人が真に自分らしいあり方で存在すること」に価値を置きました。
コーチングでも、「クライアントは“何をするか”以上に、“どう在るか”を選べる」という考え方が核になっています。
要するに、Doingモードに傾きがちな現代社会だからこそ、Beingモードを意識することが大切だと、さまざまな分野で語られてきたのです。
Being寄りで生きて感じたモヤモヤ(私の体験)
みなさんはこれまで、DoingとBeing、どちらを重視して生きてきましたか?
私は大学生まで、Doing(社会的成果)寄りの価値観を持っていました。
世間的に良い大学に進んで、良い会社に入って、キャリアや家庭を築く。そんな未来を当然のように思い描いていました。
ブータンでの衝撃
ところが、大学時代に訪れたブータン王国で、その価値観が大きく揺らぎました。
「日本の江戸時代の暮らし」と例えられたその場所で、物質的には豊かでなくても、人々は穏やかで幸せそうに暮らしている…。
その在り方がとっても「豊か」に見えました。そして、「社会的な豊かさではなく、自分にとっての豊かさとは?」と考え始めるようになったのです。
そこから迷路に入った私
それからは、なぜか人生が迷路に入っていきます。(おい人生よ。でも、今は感謝してます。)
ブータンがきっかけで、私はBeing(在り方)を意識するようになりましたが、同時に「社会で生きていくにはDoing(行動・成果)も必要」という現実に直面しました。
Doingに偏ると疲弊して自分を見失う、Beingに偏ると生活をどうするのかという不安が出てくる。
20代は、色々とにかく試して、そのバランスをどう取るかを模索していたように思います。
正直、今も私にとって「Doing」は課題かもしれません笑
自己対話は「Beingを整える時間」
そんなこんなで、なかなか苦戦をして生きてきた私ですが、大きな転機になったのは、Being(在り方)を腰を据えてしっかり整えたときでした。
3年ほどDoing(行動・成果)に偏っていた私は、改めて内側を整えることが必要だったのだと思います。まずBeingを整え、そこからDoingにつなげたことで、自分の人生を取り戻すことができました。
この流れを支えてくれたのが、他でもない自己対話(内観・内省)です。
自己対話は、Beingを確認し、整える時間。
「自然体でいて大丈夫だ」と思い出させてくれる時間でもあります。
そして、その整った自分で、「したいこと」「ワクワクすること」をDoing(行動)に移す。
それが、私にとっての「人生を軌道修正する方法」になっています。
📚 自己対話の目的についての記事はこちら
DoingとBeingのバランスを整える4つのパターン
私は、Being(在り方)→Doing(行動)の順番で自分を立て直しましたが、その後は状況に応じて他のパターンも取り入れています。
みなさんも「今の自分」によって、しっくりくる流れが違うかもしれません。
〈 DoingとBeing:4つのパターン 〉
Being → Doing
・まず在り方をしっかり整えてから動く
・内側が安定しているからこそ、行動がブレない
Doing → Being
・とにかく動き続ける中で在り方に気づく
・トライ&エラーから「これが自分らしい」と発見する
Doing & Being
・行動しながら常に「自分らしいか?」を意識する
・行動と内省が自然に並走する
Doing ⇄ Being
・小さく動き、小さく整えることを繰り返す
・短いサイクルで確認しながら進む
どれが正解ということではなく、どれが今の自分にとって自然かを知ることが大切です。
特にDoingに偏りやすいこの社会では、一度、意識的にしっかりとBeingを整えることが必要だと、私は考えています。
まず少し立ち止まり、ぜひBeingを整える自己対話(内観・内省)をしてみましょう🌱
あなたにとって、いま心地よいDoingとBeingのバランスはどれですか?
まとめ|DoingとBeingを見直す自己対話
ということで、今回は、DoingとBeingについて一緒に整理してきました。
「自分はDoingとBeing、どちらかに偏りすぎていないかな?」
「今の自分に合ったバランスはどんな形だろう?」
そんな問いがポツンと生まれて、自己対話につながるきっかけになれば嬉しいです。
もし一人では難しいと感じるときは、ぜひセッションの中で一緒にBeingを整える自己対話をしてみましょう。
それでは、また次回の記事で〜🍵
〈 今回の記事のまとめ 〉
- Doing=行動・社会的成果、Being=在り方・自分らしさ
- 現代社会はDoingに偏りやすく、Beingを整える意識が大切
- 私にとっての転機は「Beingを一度しっかり整えたこと」
- 自己対話は、Beingを確認し整えるプロセス
- まず少し立ち止まり、Beingを整える自己対話をしてみよう
🌱 自身の「性質・傾向」を知って、
見えなくなってしまった「本音」を一緒に探す、自己対話ナビゲーション型セッション
📚 あわせて読みたい記事
🔍 読みたい記事がありませんか?このページでは、関心ごとから記事を選べます。


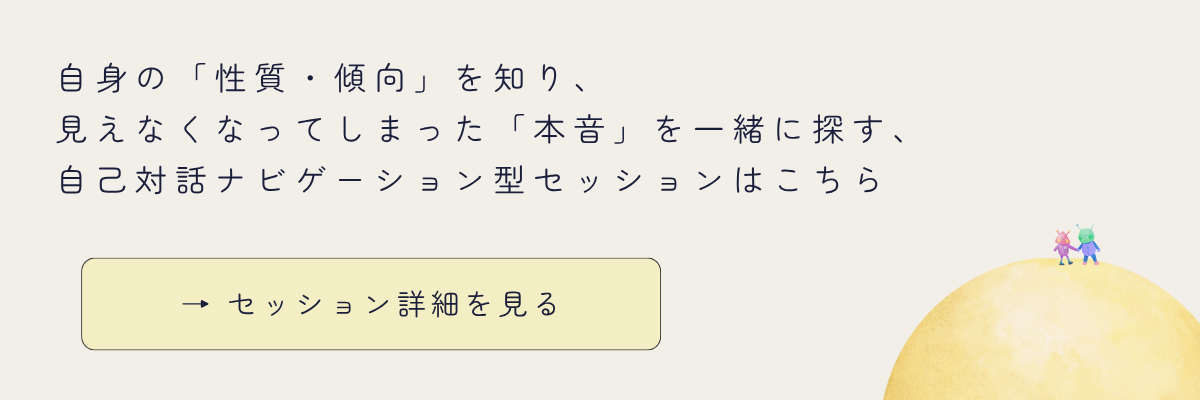



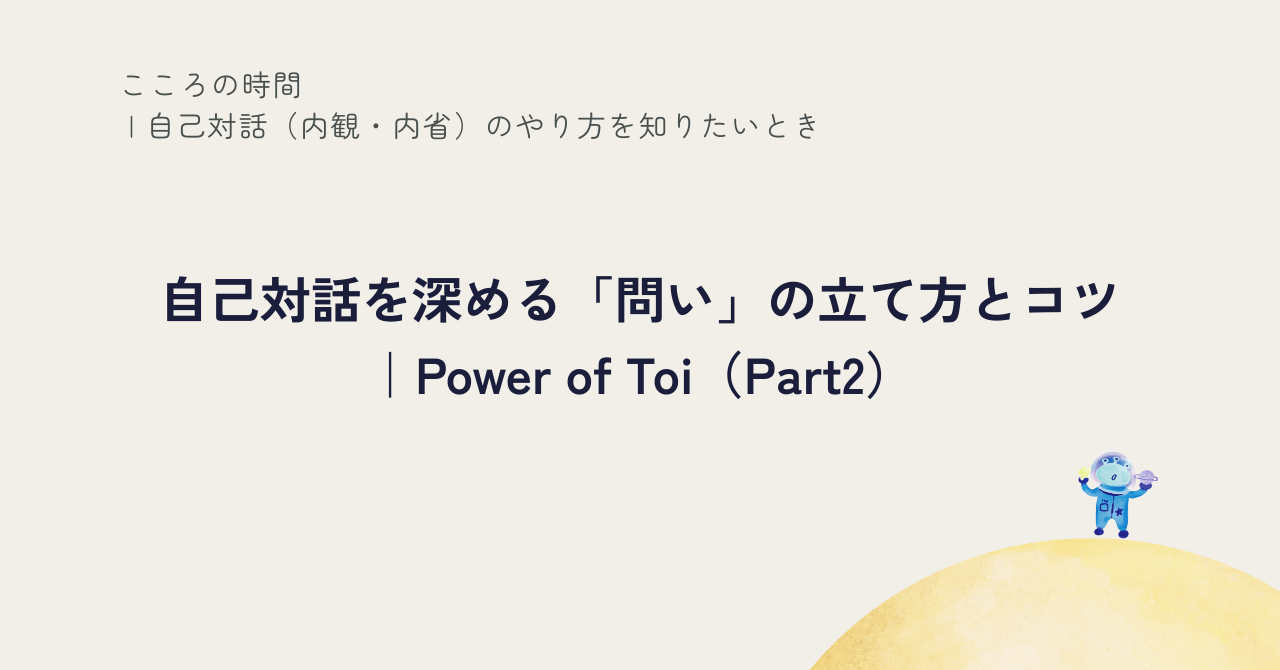
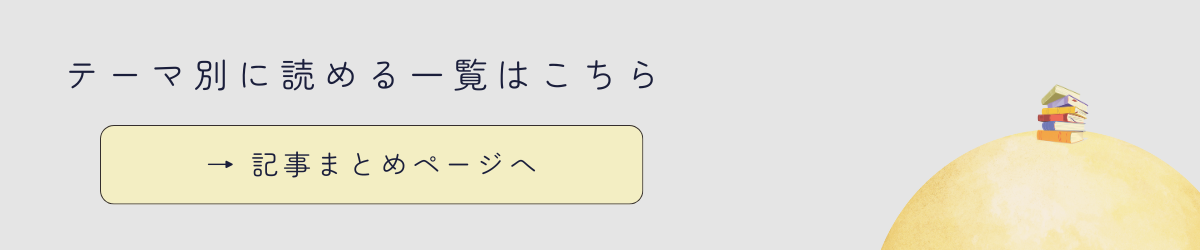
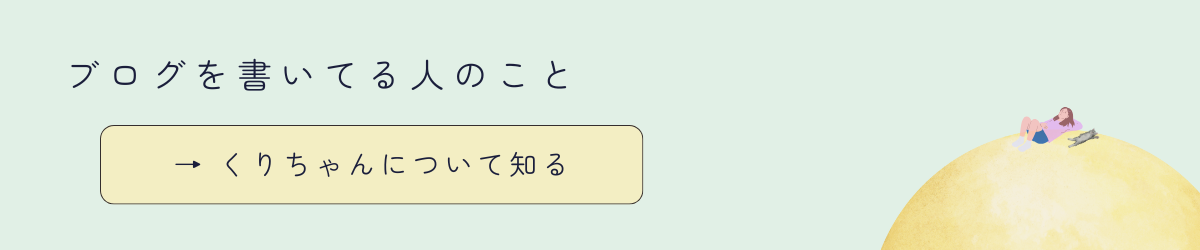
タロットって「占い」のイメージが強いですが、実は自己対話のサポートにも使えるんです。私が普段実践している「タロットで自分の本音に気づく5つのステップ」をご紹介します。