自己対話を深める「問い」の立て方とコツ|Power of Toi(Part2)
問いを立てるときに意識すること
みなさん、こんにちは。
風の音って何かに当たることで初めて聞こえるらしいです👂
言われてみればそうかも💡ですよね。
それじゃ、ヒュ〜〜って音の時は何にぶつかってるんでしょうね?
え、じゃあ口笛やリコーダーはどういう原理…?
疑問が芋づる式に湧いてくる…!
くりちゃんです。
さて、前回の記事で、Power of Toi について書きました。
(ホントはPower of Toi って言いたいだけ)
「人は、立てた問いにしか答えられない」というお話でした。
実は、今回でこのお話は完結の予定だったのですが、
思ったより記事が長くなってしまったので、3つの記事に分けることにしました📚(もう長くなっちゃうのが、あるある化しつつある)
今回は、
「じゃあ実際にどういうことを意識して問いを立てたら良いんですか?」
という問いに答える内容です。
自己対話が深まる「問い」の特徴
私が問いを立てるときに大事だと思う3つのポイント
問いを立てるのが得意な方も、苦手な方もよかったら参考にしてみてください😊
自己対話が深まる「問い」の特徴
問いは「答えを引き出す鍵」のようなものだと考えています🗝️
では、自己対話が深まる問いとは、どんなものでしょうか?
これからご紹介するものは、
カウンセリング
コーチング
コンサルティング
の現場でもよく使われる問い・アプローチでもあります。
自己対話を深める3つの基本視点(内側・前提外し・切り分け)
① 外側よりも、自分の内側に焦点がある
「あの人はどう思ってる?」ではなく「私はどう感じている?」
外的要因を変えるより、まず自分の感じ方・価値観を見つめることを優先
→ 外側のノイズを一度排除して、「自分軸」に戻れる💡
② 前提を一度外す問い
「〇〇だから無理」という条件を外してみるもの
例:「もし制限がなかったら、どうしたい?」
→ 視野を広げる時にすごく効く💡
③ 感情・思考・事実を切り分けた上の問い
この3つは混ざりやすいので、意識して切り分けることで整理しやすくなる
例:「あの発言によって、モヤモヤしているのはなぜだろう?」
→ 中庸さと客観性が保たれて、相手や自分や状況を俯瞰できる状態になれる💡
浅い問いと深い問いの違い
そして、浅い問いと深い問いの違いを、いくつかの例で、まとめてみました📝
ここで言いたいのは、
浅い問い、深い問い、どちらが良い悪いというわけはありません。
どちらも状況によって必要です。
ただ、自分の本音を知りたい時や、自己対話を深めるためには、深い問いを用意する必要があります。
つまり、浅い問いは“表面の確認”、深い問いは”内面の掘り下げ”。
ざっくりこの違いだけ覚えておけばOKです🙆
「答えを誘導しない問い」の重要性
答えを誘導しない…とは?
これはどういうことかというと、
「自分が聞きたい答えに、自分を誘導しない問い方をする」ということ
です。
特に自己対話の場合、「こうあってほしい答え」を想定して問いかけがちだったりします。
例えば、
「私はやっぱりこの仕事を続けるべきかな?」
この問いをした時点で、
なんとなく続ける前提が強めに感じませんか?
「うん、やっぱり続けるべきだ」って答えれば、
自分を納得させられて、変化もなく、楽だったりします。
無意識に前提を決めてしまうと選択肢が減ります。
ちょっとだけ比較例を出してみました👇
これは、無意識に私もよくやっています🫣
いつの間にか「〜しなきゃ」に縛られていたりして、その範囲でしか自分に問えなくなります。
中庸さや、少し客観的な視点を持って、様々な可能性に心をオープンにすることが大切だと常々思います。
もうちょっと噛み砕くと、
中庸さ(白黒を急がないこと)
客観性(視点を広げること)
俯瞰(構造として見ること)
を意識しながら、
「頭ではなく自分の内側」の答えを見に行く
「自分が知らない自分の気持ち」を知ることを楽しむ
ことです。
「え、意識すること多すぎて、問いって重労働じゃないですか・・・」と思ったそこのあなた。
大丈夫です。
ここまで色々挙げましたが、全部を一度にやる必要はありません。
ひとつでも「お、これ使えそう」と思ったものから試せばOK 👍
自己対話は、段階的に深まっていくものなので、
自分に合う方法を少しずつ見つけていきましょう。
私が問いを立てるときに大事だと思う3つのポイント
ここからは、上で挙げた中でも、
私が個人的に大事だと思う、3つのポイントをご紹介します💡
① 外側ではなく自分の内側に焦点(「私はどう感じる?」)
② 優しい眼差しで事実を見る(中庸・客観)
③ 予想外の自分を面白がる(受容と発見)
生きているだけで、自然と外側の情報が入ってきて、
「〜しなきゃ」「〜べき」という思考が形成されがちです。
だからこそ、「自分はどうなのか」に視点を戻すことが一番大事だと思っています。
そして、その眼差しは冷静だけど温かく優しいもので。
それがジャッジしすぎない、中庸さにつながります。
「すごい」自分を発見する時も、
「社会的にはちょっと非常識かもしれない」自分が見つかる時もまた面白いです。
つまりは、自分に優しい眼差しで寄り添って、どんな自分も面白いじゃんと受け入れる。
この意識があれば、問うことは、そこまで怖くないことかもしれません🌱
まとめ
今回は、
良い問いってなんだろう、
浅い問い深い問いってなんだろう、
というところを言語化してみました。
私の願いとしては、
自分をジャッジするような問いではなく、
自分を優しく見守って、共感して、知ってあげるための問いが
もっと広まれば良いなぁというところです🪷
その積み重ねが、自分と仲良く生きる土台になります🏠
次回は、
くりちゃん式問いの立て方
すぐに使える問いのテンプレ(今モヤモヤしてる方におすすめです)
で、このシリーズを締め括ろうと思います。
来週、またもう少しお付き合いください🍵
📚続きのPart3はこちらから👇
🌱 自身の「性質・傾向」を知って、見えなくなってしまった「本音」を一緒に探す、自己対話ナビゲーション型セッションはこちら
📚 あわせて読みたい記事

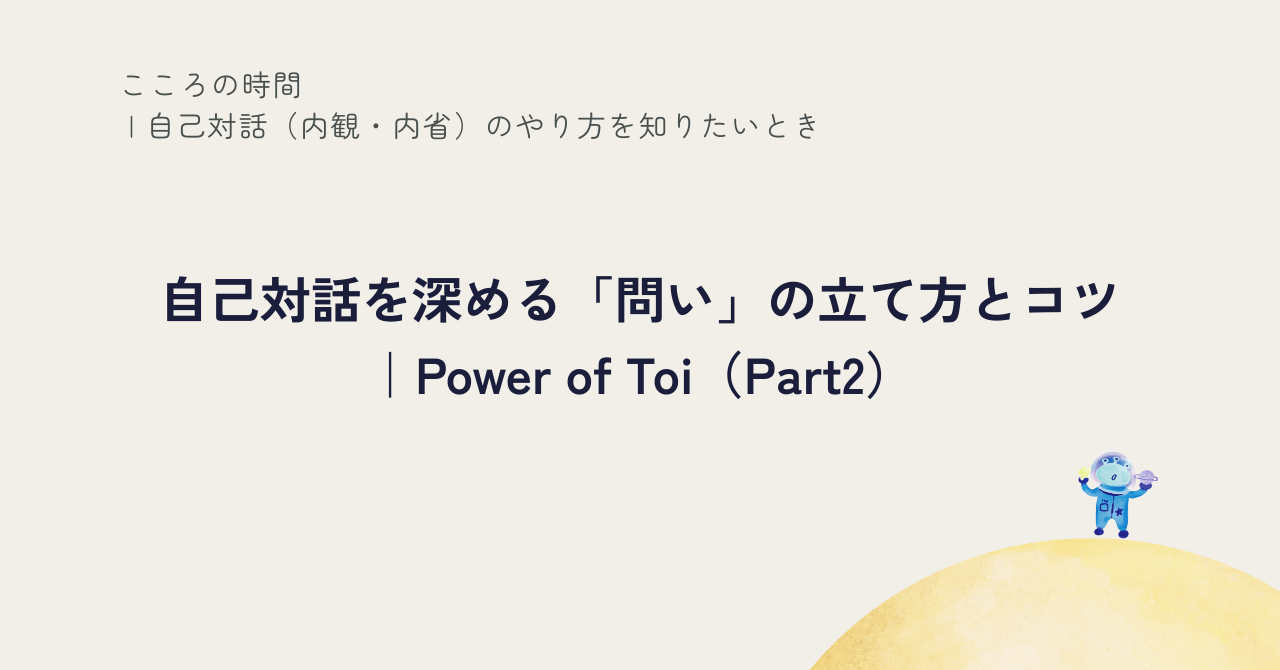







タロットって「占い」のイメージが強いですが、実は自己対話のサポートにも使えるんです。私が普段実践している「タロットで自分の本音に気づく5つのステップ」をご紹介します。