十牛図とは?|「自分を見つける旅」を描いた禅のガイドマップ(Part1)
みなさん、こんにちは!くりちゃんです。
十牛図(じゅうぎゅうず)って、聞いたことありますか・・・?
十牛図は、禅の教えから生まれた10枚の絵です。
「牛」は、禅では心や仏性(ぶっしょう)を象徴し「煩悩に覆われた心」を修行で飼いならしていくプロセスとして描かれます。
現代では、牛は、「真の自己」「本当の自分」「ありのままの自己」「魂の本質」などの象徴としても語られたりもします。
“牛を探す物語”=“自分を見つける旅”として解釈することが可能です。
迷って、探して、見つけて、そしてまた日常に戻る。
そんな「内面の旅」を描いた、ちょっと不思議で奥深いガイドマップです。
今回の記事は、十牛図を簡単に解説しながら、
現代の私たちにとっての「自己対話(内観・内省)」や「自己受容」とのつながりを丁寧に見ていきます。
ぜひ、「自分は今どのフェーズだろう?」と照らし合わせながら、読んでみてください。
私と十牛図の出会い|2023年・韓国の山寺で感じた“自分探し”の原点
十牛図に初めて出会ったのは、2023年の夏。
日本の友だちが韓国に遊びに来てくれた時に一緒に行った、百潭寺(ペクダムサ -백담사-)という山奥のお寺でした。
お寺の建物の壁に描かれていて、「あれなんだろう?」と友だちが気づいたのがきっかけでした。
まずは、その壁に描かれていた実際の絵をもとに10枚の図を紹介しますね。
影になっているものもあって、見にくかったら申し訳ないです。
画像をクリックすると一枚ずつ拡大して見られます。
なんか可愛いですよね。10コマ漫画みたいです。
この図の原典は、12世紀の中国・宋代の禅僧「廓庵(かくあん)」によるもので、「悟り」に至るまでの道のりを描いたもの。
図だけで物語を想像するのも楽しいですが、少し分かりにくい部分もあるので、ここからそれぞれの意味を解説していきますね。
絵で見る十牛図の流れ|悟りに至る“心の旅”の10フェーズ
それでは、①~⑩のフェーズを見ていきましょう。
先ほども触れましたが、禅では「牛」= 心や仏性(ぶっしょう)つまり「煩悩に覆われた心」を象徴します。
この記事では、より身近に感じてもらえるように
「牛」=「自分らしさ」
と捉えて読み解いていきます。
シンプルに描かれているからこそ、深くて普遍的。
一見わかりやすく見えて、わかりにくい。実はとても奥が深い図なんですね。
🐃 十牛図の10フェーズ
- ① 尋牛(じんぎゅう):牛(=自分らしさ)を探しに旅立つ
- ② 見跡(けんせき):牛の足跡を見つける
- ③ 見牛(けんぎゅう):牛の一部が見える
- ④ 得牛(とくぎゅう):牛をとらえる
- ⑤ 牧牛(ぼくぎゅう):牛を飼いならす
- ⑥ 騎牛帰家(きぎゅうきか):牛に乗って帰る
- ⑦ 忘牛存人(ぼうぎゅうぞんにん):牛(自分らしさ)を忘れ、人(自我)が残る
- ⑧ 人牛倶忘(にんぎゅうぐぼう):人も牛も忘れる(空の境地)
- ⑨ 返本還源(へんぽんかんげん):原点に帰る(本来の自己)
- ⑩ 入鄽垂手(にってんすいしゅ):人里(本来の訳は町)に帰って人と関わる
悟りは終わりではなく、日常へ戻る道
十牛図のラスト(⑩入鄽垂手)で描かれているのは、
悟りを開いたあとに「人里へ戻り、人と関わりながら自然体で生きていく姿」です。
ここが、十牛図で特に好きな部分。
初めてそれを知ったとき、「え、悟り開いたらそれで終わりじゃないんだ!?」とびっくりしたのを覚えています。
「悟り」を開いたら、仏様みたいな存在になってそれで「完了」だと思っていたからです。
人里に降りて、「悟り」を開いた自分で、生きていく。
その在り方だけで、人にもやさしい循環を生む。
結構現実的というか、なんかやさしい思想ですよね。
そう考えると、「悟り」ももっと身近に感じられるかもしれません。
わたしにとっての牛とは?|“自分らしさ”を探す自己対話のはじまり
私がこの十牛図に出会った時、
「牛」が一体全体何を指しているの全然分からなかったんですよね🐃
そもそも「牛」って何?
というか「悟り」がどう言う状態かすら分からない。
当時の私にとっての「牛」は、「やりたいこと」だったように思います。
だからこそ、「やりたいこと」を探す旅に出ました。
ただ、「やりたいこと」はなかなか見つからず、焦りもあったし苦しかったです。
そして、そのまま十牛図のことはすっかり忘れてしまいました。
その後、自己対話(内観・内省)を通して、
「自分を受け入れること」を体感してから、久しぶりに十牛図を見返してみると、
まさに「自己受容へと向かうプロセス」を含むものだったことに気づいたんです。
今の私にとって「牛」は、「自分らしさ」に変わりました。
十牛図を現代風に読み解く|“心のプロセス”で見る自己成長の10フェーズ
自分を探し始め、自己受容をして、自分らしく生きて、それすら手放した先がこの十牛図には示されています。
ここからは、十牛図を自己対話(内観・内省)や自己受容に準えて、現代風に読み解いてみます。
私の体感の部分もありますが、みなさんの自分探しの旅のヒントになれば嬉しいです。
🐃 現代版“心の旅”をざっくりまとめました
1行ずつ、①〜⑩を1文でざっくり表にまとめました。
🐃 十牛図のステップ |
現代的な意味 |
心のプロセス |
|---|---|---|
| ① 尋牛 (じんぎゅう) |
“自分らしさ”を探すと決める | 自己対話のはじまり |
| ② 見跡 (けんせき) |
“自分らしさ”のカケラを 見つける |
内観フェーズ (感情に気づく) |
| ③ 見牛 (けんぎゅう) |
“自分らしさ”を 部分的に理解する |
内省フェーズ (自己理解) |
| ④ 得牛 (とくぎゅう) |
“自分らしさ”の軸をつかむ | 自己受容のはじまり |
| ⑤ 牧牛 (ぼくぎゅう) |
“自分らしい”行動を重ねる | 自己対話と実践 |
| ⑥ 騎牛帰家 (きぎゅうきか) |
“自分らしく”生きることが 定着する |
自己受容の定着 |
| ⑦ 忘牛存人 (ぼうぎゅうぞんにん) |
“自分らしさ”から自由になる | 心理的・感情的統合 |
| ⑧ 人牛倶忘 (にんぎゅうぐぼう) |
ただ在る | 存在的統合 |
| ⑨ 返本還源 (へんぽんかんげん) |
生命としての自分に戻る | 自然体の自己信頼 |
| ⑩ 入鄽垂手 (にってんすいしゅ) |
自然体で人と関わる | 外の世界との 統合と循環 |
📘 詳しく見る|“自分を見つけ、受け入れ、手放す”心のガイドマップ
💡 先の表の各項目の内容を、ガイドマップとしてより詳しくまとめました。
右横の「+」をクリックまたはタップすると内容が見られます。
-
🐃 十牛図のステップ:
牛(=新の自己)を探しに旅立つ
💬 現代的な言い換え:
“自分らしさ”を探すと決める
・「私、このままでいいのかな?」という問いが芽生える
・モヤモヤや違和感に気づいて、自分について考えるようになる🪞 自己対話のはじまり:
外側ではなく内側に問いを向け始める。心の探求がスタートする。
-
🐃 十牛図のステップ:
牛の足跡を見つける
💡 現代的な言い換え:
“自分らしさ”のカケラを見つけていく
・自分の好きなこと、嫌なことなど、「自分らしいかもしれない部分」に気づく
・疲れ、怒り、寂しさ、嬉しさ、楽しさなど体や感情のサインが「本音の入り口」になる👀 内観フェーズ:
感情や体感に注意を向け、心の動きを見つめる力が育ち始める。
-
🐃 十牛図のステップ:
牛の一部が見える
💬 現代的な言い換え:
“自分らしさ”を部分的に理解する
・自分が「本当は何を大切にしていたか」に気づき始める
・本音・本当の望みに触れる🔍 内省フェーズ(自己理解):
出来事の意味を考え、心の奥にある意図やパターンを整理し始め、自分を知っていく。
-
🐃 十牛図のステップ:
牛をとらえる
💬 現代的な言い換え:
“自分らしさ”の軸をつかむ
・自分の価値観を見つけ、受け入れる
・もう逃げずに「自分の軸・核」と向き合う覚悟ができる💛 自己受容のはじまり:
気づいた“自分”を否定せず受けとめ、少しずつ無条件の安心を取り戻す。
-
🐃 十牛図のステップ:
牛を飼いならす
💬 現代的な言い換え:
“自分らしい”選択や行動
・時に揺れながらも、「これが私」と思える選択を重ねていく
・自分を整えながら、自分軸で行動し始める🌱 自己対話と実践:
日々の選択の中で、感情や思考と向き合いながら整える習慣が根づく。自己受容が少しずつ育っていく。
-
🐃 十牛図のステップ:
牛に乗って帰る
💬 現代的な言い換え:
“自分らしさ”をベースに生きられるようになる
・自分らしく生きることが定着する🏠 自己受容の定着:
自己受容が深まり、「私はこれでいい」という穏やかな自己信頼が生まれる。自我の健全な完成。
-
🐃 十牛図のステップ:
牛を忘れ、人(主体)が残る
💬 現代的な言い換え:
“自分らしさ”から自由になる
・“自分らしさ”(自我 = エゴ)を意識する必要がなくなり、手放される
・自分(主体)だけが静かに在ると認識し、承認や証明が必要なくなる🕊️ 心理的・感情的統合:
証明や承認の手放し。
“自分らしくあろう”という意識すら薄れ、静かな自由が広がる。
思考と一体化しない静けさが生まれる。 -
🐃 十牛図のステップ:
人も牛も忘れる(空の境地)
💬 現代的な言い換え:
ただ在る
・自分という主体(気づいている私)すらなくなっていく
・ただ、何者でもない自分がそこに在るだけ🧘 存在的統合:
観照者としての自分すらなくなり、“ただ在る”という感覚に溶けていく。
-
🐃 十牛図のステップ:
原点に帰る(本来の自己)
💬 現代的な言い換え:
生命としての自分に戻る
・自然や周りにあるもの、その循環の一部になり、生命としての自分に戻る
・個としての境界が溶ける🌳 自然体の自己信頼:
自然の循環の中に自分を感じ、「あるがままでよい」と深く信じられる。
-
🐃 十牛図のステップ:
手ぶらで人里に戻る
💬 現代的な言い換え:
社会に戻り「自然体の生き方」を実践する
・ふたたび他者と関わる
・自分を語らずとも、在り方そのもので場がやさしく整うような境地🚶♀️ 外の世界との統合と循環:
在り方そのもので人と関わり、やさしさを自然に循環させていく。
自己受容にもフェーズがあって、十牛図でいうと④~⑦のあたりを指しています。
結構幅が広いですよね。
それぞれの段階で、少しずつ深まりながら、自分自身との関係性が変化していくのが特徴です。
健やかに自分らしく生きるには、「自己受容」の深まりは欠かせないものだと私は考えています。
『自分らしさ=煩悩』という気づき
「自分らしさ」は一見“光”のように見えて、実は“こうありたい”“こう見られたい”という自我の声(煩悩)でもあったと気づきました。
でも、その“自我の声”を通して自分を探していくことこそ、自己対話のはじまりであり、通過すべき大切なプロセスなのだと思います🌱
自分らしく生きることは、必要なプロセス。
自分らしく生きるには、自己対話(内観・内省)と自己受容がカギ。
十牛図の歩み方|ゆっくり一歩ずつ
この10枚の図、例えば、3から8にジャンプしたり、そんなことは可能でしょうか?
私は、この十牛図の10ステップは、全てを通過することが必要だと考えています。
ひとつひとつ進みつつも、④と⑤を行き来したり、⑦にいたと思ったら⑤に戻る。そんなことはあり得るかもしれません。
そんなこんなを繰り返しながら、最終的に全ての段階を経験することが、「人として成熟する」ことなのではないかなぁと思っています。
たとえ前のステップに戻ったとしても、それは後退ではなく、統合のための再訪。より深いレイヤーで学び・経験しながら通過していく。
それは、一直線でなく螺旋で成長していく人生を描いているようでもあります。
私たちは、同じ場所をぐるぐる回っているように見えても、
実は少しずつ深い層で理解し、統合しているのかもしれません。
焦らず、進んでいけば、いつの間にか次の図の段階に移っている。
ある日、「あれ、変わったかも」と変化に気づいて、初めて自分のいるフェーズを実感していくもんなんだろうなぁと思っています。
前の状態に戻っても、それもプロセスの一部と考え、焦らず生きる。
それはとってもゆるやかなペースです。
牛(自分らしさ)を見つける鍵|自己対話で本質とつながる方法
まず、あなたの「牛」を見つけるには、こんな方法が役立ちます。
① 内観
自分の感情や思考に、まずは気づいてあげる
② 内省
「なぜそう感じたのか」「本当はどうしたいのか」と自分に質問しながら整理していく
③ 自己受容
自分の本当の気持ちに共感して、認めてあげる
やがて、そのままの自分で良いと受け入れられる
私は、内観と内省をまとめて、「自己対話」と呼んでいます。
全ては、自分の中に答えがあり、
「やりたいこと」も「自分らしさ」もすでに自分の中にあると私は考えています。
実は、そこにずっとあるんだけれども、
育つ過程や、環境・教育・社会的価値観・出会う人たちの影響で、
良くも悪くも「自分らしさ」というのは見えなくなってしまうことが往々にしてあるんですよね。
自己対話は、外側のガラスについた曇りを、少しずつ拭き取っていくようなもの。
自分の「本当の気持ち」は、いつもその向こう側にいます。
そして、その自分を大切にしながら生活すると、現実が変わっていきます。
山に籠って修行するのも一つの方法ですが、
日々の暮らしの中で、自分の感情を観察したり、
一人静かにお茶を飲む時間を持つことも、現代の「修行」かもしれません。
私もまだ道半ばですが、一緒にゆっくり一歩一歩進んでいきましょう。
📚 自己対話(内省・内観)の詳しい方法はこちら
📚 自己受容について詳しく知りたい方はこちら
まとめ|自分を探す旅に終わりはある?
さて、ここまで私なりの解釈で十牛図を紹介してきました。
十牛図を少し身近に感じてもらえていたら嬉しいです。
本当の自分を見つける旅に終わりはあるのでしょうか?
もしかしたら、この人生で見つかることもあるかもしれないし、ないかもしれない。
誰もがそれぞれの経験を通して、学び、成長していく。
そのこと自体が、すでに尊いんですよね。
十牛図通りに生きようとする必要はないですし、あくまでこれはガイドマップです。
寄り道したり、戻ったり、目的地に行かないことも、選べます。
でももし、必要な時は参考にしたり、これまでの道の振り返りに活用してみてください🌱
ここまでお読みいただきありがとうございました。
それでは、また次回の記事でお会いしましょう〜🍵
〈 今回の記事のまとめ 〉
- 十牛図とは:心を探し、受け入れ、手放していく“内なる旅”の地図
- 牛の意味:“自分らしさ”や“本当の自分”の象徴(=自我・煩悩を含む)
- 自己対話の役割:内観・内省を通して、心の声に気づくことが「牛を見つける」第一歩
- 自己受容の段階:④〜⑦のプロセスで「ありのままの自分」を受け入れていく
- 進み方:スキップ不可。螺旋を描くように、行きつ戻りつしながら成熟する
- 実践のヒント:日常の中で感情を観察し、静かな時間を持つことも“修行”のひとつ
- 最終地点:悟り=終わりではなく、“自然体で生きること”そのもの
🌱 自身の「性質・傾向」を知って、見えなくなってしまった「本音」を一緒に探す、自己対話ナビゲーション型セッション
📚 あわせて読みたい記事
🔍 読みたい記事がありませんか?このページでは、関心ごとから記事を選べます。












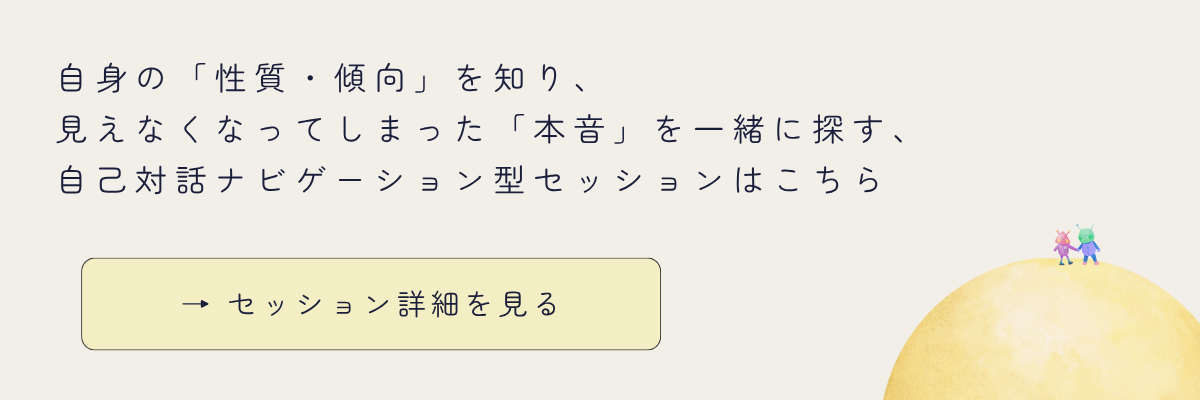


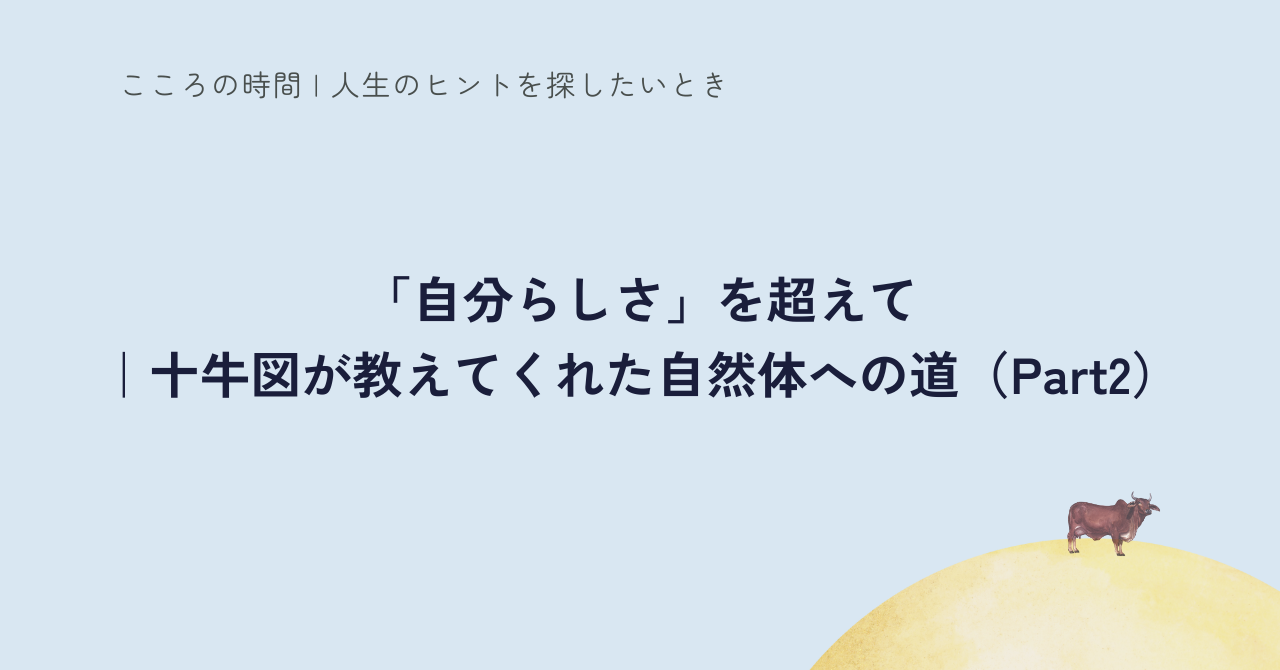
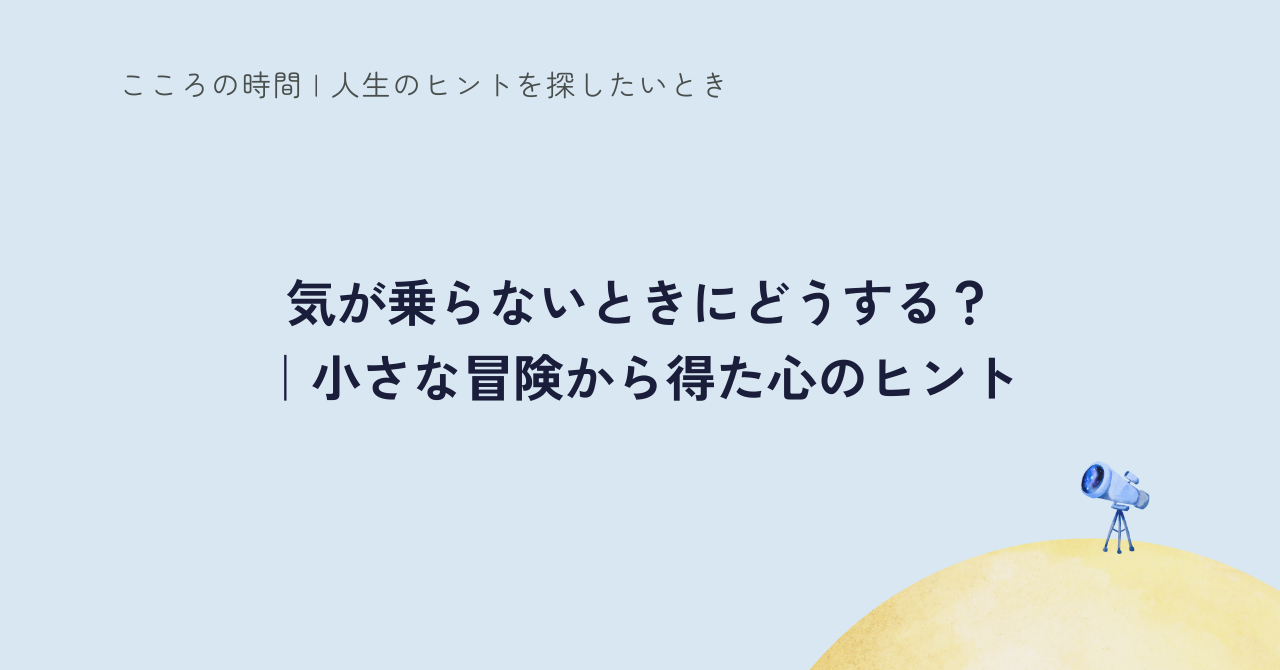
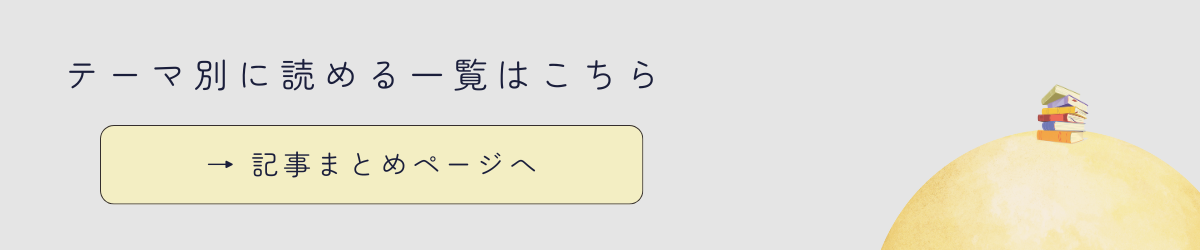
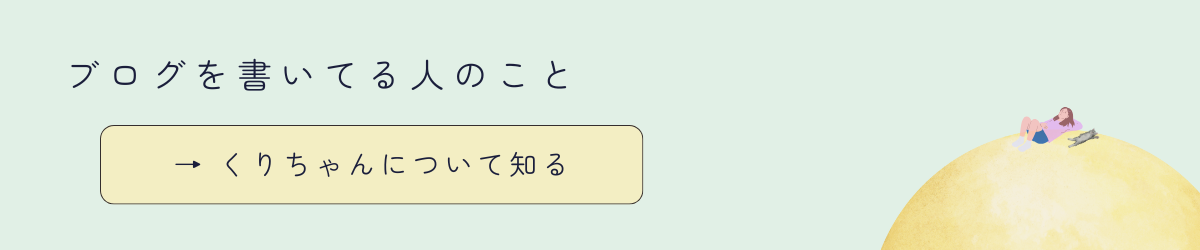
前半では、自己啓発の言葉を「火・風・土・水」の4タイプに分類しました。後半では、それぞれの言葉と人の気質の相性、そして振り回されないために必要な「自分を知る」視点をお届けします。